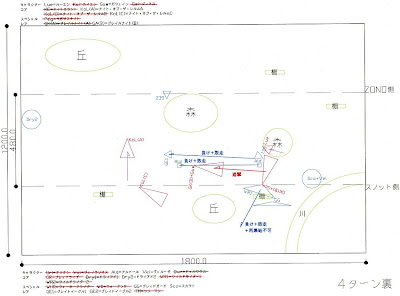アルドールの協力を取り付けたヴェイラリオスは、新たな戦士を戦列に加えるべくドゥルワウスの林へと出向いたのだが・・・
ロゥレンの森の中でもアスライが近寄らない場所がある。 今ヴェイラリオスが馬を進めているこの荒ヶ森周辺もその1つだった。
アルドールを伴って王君の樹林に戻ったヴェイラリオスは、間を置かずにこの林に向かったのだ。
ブランチレイス(古枝の霊)“とねりこ”のドゥルワウスと彼女の侍女であるドライアド達を今度の戦に加勢させる為だ。 ドゥルワウスは荒ヶ森に近いこの林に居を構えており、この辺りは「ドゥルワウスの林」と呼ばれていた。
「ロゥレンに侵入者あり」の時にはアスライ達が動くよりも早くドライアド達が侵入者を血祭りに上げるし、また“樹海の王君”オリオンがその大角笛を吹き鳴らし「血の祝祭」に出かける時には彼女達も嬉々としてその残酷な祭りに出かけるのだが、今回のような国軍同士の試合に、気まぐれな彼女達がはたして応じてくれるかどうかヴェイラリオスにも疑問だった。
とは言えあの木霊達の力が今度の戦いに無くてはならない物だった。
ヴェイラリオスは今、鎧に身を包んでいた。 何しろ彼女達、特にドゥルワウスは気まぐれで通っていたし、仲間や味方の意識は有ってもアリエルやオリオンに対して主君としての敬意は持ち合わせていなかった。(精霊の中にはあからさまに敵意を抱く者すらある)
その為に、以前にも彼女を招集しに行ったアスライの貴人がうっかり口の利き方を間違えて八つ裂きにされた事が有るのをヴェイラリオスは知っていた。
「用心に過ぎたるはなし」
と言うことだ。
その昔「裏切り者」として知られるツリーマンの長老コーディルを閉じ込められた荒ヶ森は、妖しげで邪な力の影響を受けて見る者に禍々しい印象を与えるのだが、外周に置かれた結界の外は、ロゥレンの森が本来持つ風景を留めていた。
ヴェイラリオスが「ドゥルワウスの林」に踏み込んでどれ程進んだ事か、彼の耳にひそひそ話す微かな声が流れ込み、時折誰かがヴェイラリオスを覗き込んでいた。
鋭敏な感覚を持つ彼にはそれがエルフの娘のである事が感じ取れた。
もっともそれが本当のエルフでないことはヴェイラリオス自身がとうに解っていた。
「ドゥルワウスの娘達だな。“楽園の騎士”ヴェイラリオスが訪ねて来たと伝えてくれ。」
ヴェイラリオスは彼の周りで隠れている娘達に自らの訪問を告げると、間もなくその者達が姿を現した。
それらはいずれも美しいエルフの様な娘で、彼女達は薄絹を纏ったのみで、着物を透き通してその華奢な体付きが見て取れた。
確かに美しいが、ヴェイラリオスは彼女達のもう一つの姿を良く知っていた。
魔力でねじれた禍々しい樹木のようなあの姿を… 娘達は軽やかに笑いながらヴェイラリオスを林の奥へと誘った。
それを見て彼は小さく長い口笛を吹くと、彼の鎧の下から手のひらに乗るほどの大きさの、蜘蛛の様な奇妙な生き物が這い出してきた。
その「蜘蛛」はヴェイラリオスが指差した樹にお尻から飛ばした糸をくっつけ、それを見てからヴェイラリオスは、彼女達の後をついてゆっくりと馬を進めていった。
ドライアド達に誘われて馬を進めると、だんだんもと来た道が解らなくなって来た。
おそらくもとの道も変わっていることだろう。
「やっぱりな、糸を残しておいて良かった。」
ヴェイラリオスは呟いた。
これがドライアド達の常套手段だった。
時々旅の求道騎士が武勇伝を残してやろうとロゥレンの森に踏み込む事があるが、そんな輩がドライアド達の美しい姿に惹かれて彼女達の領域に迷い込み、その短い命を(本当に短いが)終える等と言う事は、こうした話にはお決まりの結末だった。
そうして馬を進めていくと暫くして開けた広間のような場所に到着した。
ここがドゥルワウスの謁見の間だった。
ドゥルワウスは奥に立つ樹の枝に腰掛けていた。
彼女も他のドライアドと同じような「姿」をとっていたが、緑色の髪は木の枝や蔦の様に捩れており、やや赤みを帯びた肌には樹皮が衣とも肌ともつかぬ様子で覆っていた。
「ようこそ、ヴェイラリオス。 “楽園の騎士”の訪問を受けるとは光栄ですわ。」
“とねりこ”のドゥルワウスは広間に到着したヴェイラリオスにそう声をかけた。
「こちらこそ、お目通り叶いまして光栄に御座りまする。」
ヴェイラリオスは、一見恭しい言葉遣いで返したが馬から下りることは無かった。
「早速だが、ドゥルワウス。久しぶりに俺に加勢して頂きたい。 この程エスファンの野において4つの国軍の試合があるのだ。 是非にもあなたとあなたの侍女達の力が必要だ。」
彼は早速ドゥルワウスに用件を述べると、それに対して彼女はこう言った。
「試合とは悠長ね、このロゥレンが危機を迎えるわけでもないのにあなたの主人の面子を立てる為に私達が出て行く事は無いでしょう? それよりあなたもそんな試合は止めにしてここで私達とのんびり遊んでいきなさいな。」
粗方予想したとおりの返事であったが、彼も手ぶらで帰るわけには行かなかったし、ましてやこの林で木の精霊達と呑気に時間を潰すつもりは毛頭無かった。
「悪いが俺はあなたと遊んでいる訳にはいかない。 それに今回の試合は森の存亡に無関係な事では無いのだ。 まあ詳しい事は後でヴェルーダにでも聞いてくれ。」
彼がヴェルーダの名を口にするとドゥルワウスは少し不快さを表してこう言った。
「あの女は女王の目付なのでしょ?女王の監視を受けながら戦場に赴くなんて窮屈でしょうがないじゃないの。 あんな女の事を話すのは止めてくださいな!」
「俺はこれでもオリオンの近衛なのでね、それにあなたの本当の姿を知っている俺はここで享楽に耽る事などできはしないよ。」
ドゥルワウスが激するかも知れないことを承知で、ヴェイラリオスはこう返すと、案の定ドゥルワウスの緑色に光る目の奥には怒りの炎が燃えるのが見て取れた。
しかし次の瞬間ドゥルワウスの目には悪戯っぽい光が現れた。
「そうね、私のような化け物と戯れるのはお嫌でしょうね。でもこういうのはどう? 今からあなたと私がこの爪とその槍とでお手合わせをしましょう。あなたが勝てばエスファンにも一緒に出向いてあげても良くってよ。」
(ようやくやる気になったか)
そう思いヴェイラリオスは内心ほくそえんだ。
槍を持って戦えばヴェイラリオスは誰にも負けない自負を持っていた。
「良かろう!して場所はどこで?」
「今すぐ、この場よ!」
彼に質問を返すが早いか、彼女はその髪を延ばしてヴェイラリオスを絡め取った。
既に彼女の爪は長く伸び、牙をむいたもう一つの「姿」を現していた。
「悪く思わないでね。これであなたに勝ち目はないでしょ?」
勝ち誇る彼女がのど元に爪を当てようとすると、ヴェイラリオスはさっきの「蜘蛛」を呼び出して、ドゥルワウスに向かって糸を吐きつけて彼女をその糸に絡め取った。
「近頃「糸吐き」を飼っているんだよ。 これで遊びが終わりなんてつまらないだろう?」
二人は絡まった糸と髪の中でもがきながら、爪と槍とを打ち合わせ続ける羽目になったが、次第にヴェイラリオスの槍がドゥルワウスを掠めるようになった。
こうして幾度目か槍を付ける内に、とうとう彼女の鳩尾に槍を付けた。
「どうやら勝負あったかな?良ければこの髪を納めてくれないかな?」
ドゥルワウスはやや不満げであったが、その髪を元に納めて先程の「姿」に戻ると忌々しげに言った。
「良いわ、今度はあなたに加勢してあげる。 ひとつ貸しておくわ。」
そんな訳でヴェイラリオスは、なんとかドライアド達の協力を取り付ける事ができた。
(戦の前に余計な仕事をしたな)
ヴェイラリオスはため息をついた。